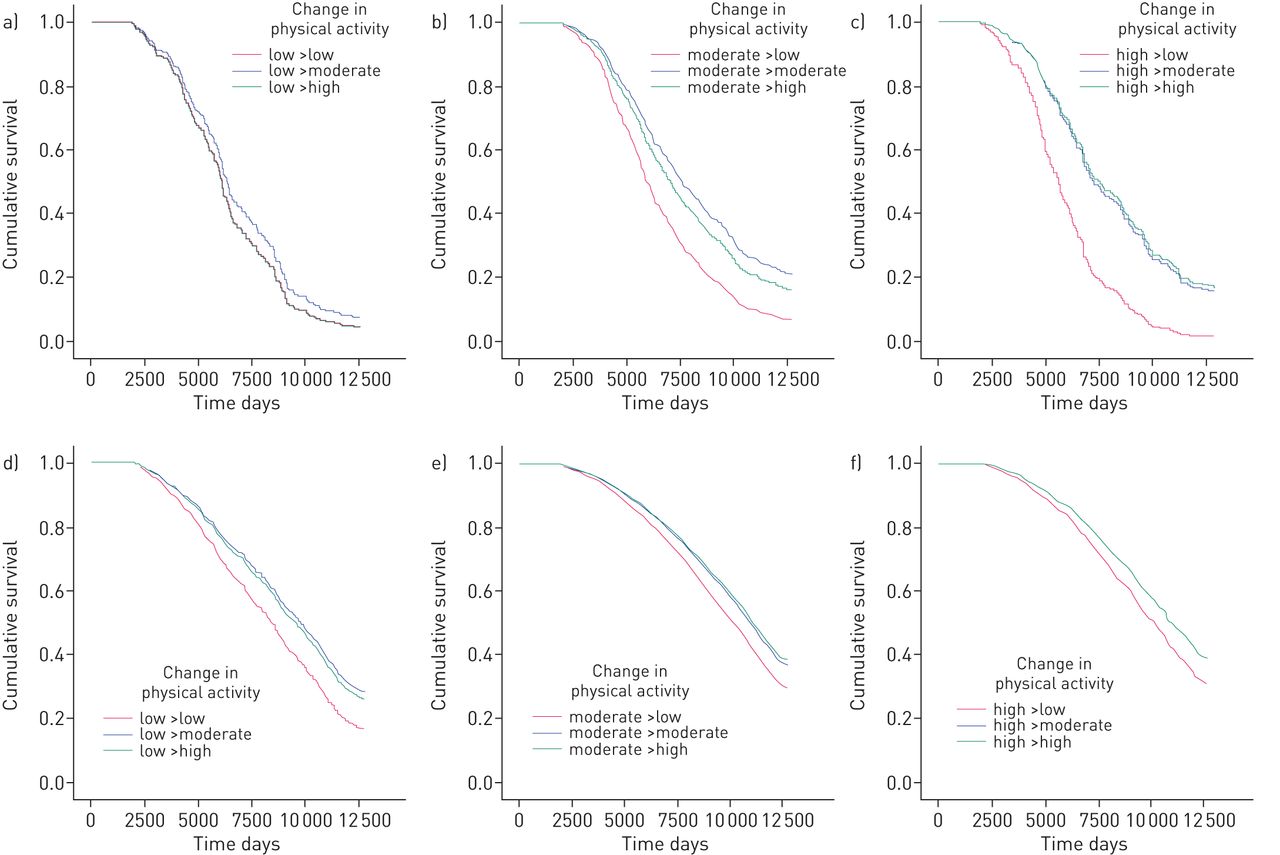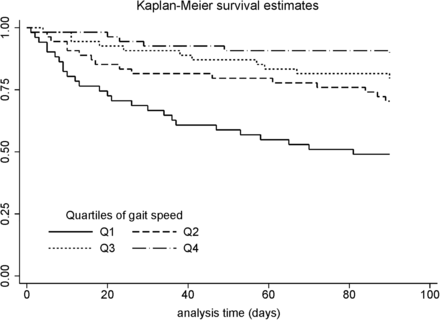Short Physical Performance Battery and all-cause mortality: systematic review and meta-analysis.
BMC Med (IF: 8.285) 2016 Dec 22;14(1):215.
<背景>
SPPBは、下肢のパフォーマンス状態を評価するためによく使用されツールである。
死亡率を予測するという報告が散見されるが、患者の状態が異なるため、結果が混在している。
この研究の目的は、SPPBスコアと死亡率についての関係をメタ解析で検討すること。
<方法>
対象文献は、MEDLINE, the Cochrane Library, Google Scholar, and BioMed Centralで2015年9月から2016年1月まで収集。
採用基準は、対象者が50人以上で、SPPBスコアで患者を層別化している、死亡率に関するデータが示されている、英語であること。
24文献がエビデンスとなり得る対象に選ばれた。
対象データを文献から抽出。年齢、性別、BMIを補正し、オッズ比や危険率でSPPBカテゴリーによる死亡率を算出。
<結果>
標準化されたデータは、17文献(n = 16,534, mean age 76 ± 3 years)。
SPPBスコア10-12点と比較して、0-3点(OR 3.25)、4-6点(OR 2.14)、7-9点 (OR 1.50)は、それぞれ死亡率の上昇と関係していた。
SPPBスコアが低いことは、フォロー期間、対象者、地域、年齢と独立して、全原因の死亡率と強く関係していた。
ランダム効果モデルのメタ回帰では、若年で、糖尿病の男性では、SPPB7-9点が最も死亡率が高かった。
<考察>
SPPBスコアが10点以下では、全原因の死亡率が上昇する。臨床でのSPPBの実施は、死亡率を予測するための有効なツールであるかもしれない。
さらに、SPPBは、研究において、死亡率のエンドポイントの代わりとしてなり得るかもしれず、特異的な治療やリハビリプログラムの効果や改善の度合いについて検討する必要がある。