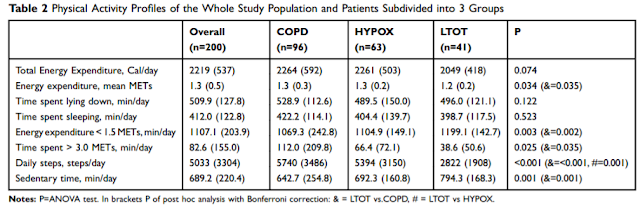Exercise training as part of lung cancer therapy
Respirology (IF: 4.88; Q1). 2020 Nov;25 Suppl 2:80-87.
<要旨>
運動療法は、肺がん治療で重要な役割を担う。肺がんは、個人医療制度の負担増加と関連している。
現在のエビデンスは、運動は、安全で実用的であり、肺がん患者(特に非小細胞肺がん:NSCLC)のアウトカム改善が得られる。
運動は、早期肺がん、周術期、進行した肺がんなどの肺がん疾患と治療経過全体で有効である。
このレビューでは、早期肺がんおよび末期肺がん患者において、健康アウトカムに影響するか、運動の安全性、有効性について述べる。
また、現在のトピックとして、骨転移のある患者への運動や腫瘍の進行の抑制効果についても議論する。
最後に、7つの臨床疑問も含め、次の10年間に優先的に検証すべきことを述べる。
・過去10年間で運動療法の安全性や実用性などのエビデンスが蓄積された。肺がん患者の運動に関する論文は、38件、システマティックレビューは20件報告されており、特にNSCLCに関する報告が多い。
【手術適応肺がん患者の運動療法】
・早期(手術適応)肺がんで手術を行う際の外科的治療パスの管理において、運動は有効な手段である。
・術前や術後の短期間(入院中)、術後の長期管理も含まれる。
<術前>
・診断から手術までの間に行われる。
・多職種チームで手術適合を高めるために行われるが、運動のために手術が遅れるというエビデンスはない。
・目的は、運動耐容能を高めることと、術後の患者と医療システムへの負担を最小限にとどめること。
・術後の肺合併症の予防は、ICU入室や入院日数の増加と関連しており、重要な役割を担う。
・術前の運動期間に関するRCTでは、4週間未満で行っている。この期間は、頻回に行っている(1日2回、週5日)
・運動強度は、中等度の持久力運動と高強度のインターバルトレーニング
<術後:入院中>
・術後可能な限り早期離床を行い、運動療法を開始する
・目的は、早期自宅退院
・enhanced recovery after surgery(ERAS)のプロトコルを使用。
・肺がん術後のERASプロトコルでは、術後24時間以内に離床を行うことを推奨している。
・離床を阻害するものは、低血圧と不安定さ(不真面目?unsteadness)
・上肢のストレッチは、疼痛の軽減や肩関節機能の改善に役立てられる
<術後:外来>
・目的は、回復と社会復帰
・多くのRCTでは、6‐12週間行われた。頻度は、週2-3回。
・運動内容は、有酸素運動とレジスタンストレーニング。COPD患者のプログラムと似た内容を行う。
<切除不能肺がんに対するリハビリ>
・目的:症状改善、運動耐容能やHRQOL低下の予防、薬物治療の副作用緩和
・運動内容:中等度強度の有酸素運動とレジスタンストレーニング
・筋肉痛などの骨格筋イベントが報告されているが、運動による重大なイベントは報告されていない
・効果:運動耐容能向上、不安、感情機能の改善。しかし、周術期の運動よりも明確なエビデンスはない。
・Cochrane review2018で6件のRCTが報告されている。介入期間は6-12週、週に1-5回。
対照群と比べて、6MWD、HRQOL、息切れが改善していた。息切れに対する運動の影響はいまだ不明確。
<骨転移のある患者の運動>
・肺がん患者の診断時に20-30%、経過中に35-40%の患者が骨転移を診断される
・RCT(肺がん以外のがん患者)にて、前立腺がん由来の骨転移のある男性患者において、運動は安全で自己報告の身体機能の改善が報告され、著明な骨疼痛はなかった。
・運動プログラムは、細心の注意をはらって、最小限の圧迫とせん断負荷で行う。
・骨盤、腰椎、大腿骨近位部の転移のある患者では、荷重のない有酸素運動(エルゴメーターなど)を行う。胸骨、肋骨の転移患者では、歩行などの荷重運動を行う。
・レジスタンストレーニングは、上肢、体感、下肢の運動が推奨される。離床的に、骨メタは運動の全面禁忌ではないが、スペシャリストが行うことを推奨する。
<運動の腫瘍進行に対する抑制効果>
・腫瘍動物モデルの研究で、運動が腫瘍増殖を抑えることができたと報告された。
・これは腫瘍内へのNK細胞が腫瘍増殖抑制に関わっていると考えられた。
・肺がんモデルにおいて、滑車運動を行った群で、腫瘍の大きさが58%、重さが56%減少していた。
・この腫瘍縮小の機序は、エピネフリンによってNK細胞が輸送され、それに続くインターロイキン-6の再分配とNK細胞の活性化によるものではないかと考察された。
・これは予備研究であることは注意しなければならないが、運動が、腫瘍内に免疫細胞の浸潤をもたらし、プロアポトーシス蛋白の上方修正をもたらすかもしれない。
・今後、ヒトを対象にした検討が必要である。